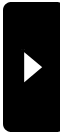生活期リハ①~生活期リハとは~
みなさん、こんばんは!
いかがお過ごしでしょうか?
今日は生活期リハについてシリーズでお届けしていこうと思います。
まずは生活期リハとは皆さんどのようなイメージがありますか?
維持期リハ
これ以上身体機能が良くならない
活動と参加にしかアプローチしない
リハの質が低い
などマイナスなイメージを持っているセラピストは少なくないと思います。
生活期リハとは、その名の通り、
「生活期」に対してリハビリ介入することです。
つまり、リハビリの対象者が
患者様⇒居住者
へと変化するのです。
その為、急性期病院や回復期病院では、患者様の疾患、身体機能へアプローチすることが多い一方、
退院すると生活をしないといけないため、生活に対してアプローチしないといけません。
または生活できている方は趣味や仕事、社会活動など今まで行っていた生活を取り戻せるようアプローチしないといけません。
そのアプローチ方法に関しては、急性期・回復期病院と同じでよろしいのでしょうか?
答えはNoです。
いくらセラピストがテクニシャンだったとしても、それだけでは解決しないのが生活期リハです。
介入方法を間違ってしまうと、いつまでたっても問題点を解決できず、リハビリ人生を送ってしまう恐れがあります。
次回は、急性期・回復期リハビリと生活期リハビリについての違いを説明したいと思います。
いかがお過ごしでしょうか?
今日は生活期リハについてシリーズでお届けしていこうと思います。
まずは生活期リハとは皆さんどのようなイメージがありますか?
維持期リハ
これ以上身体機能が良くならない
活動と参加にしかアプローチしない
リハの質が低い
などマイナスなイメージを持っているセラピストは少なくないと思います。
生活期リハとは、その名の通り、
「生活期」に対してリハビリ介入することです。
つまり、リハビリの対象者が
患者様⇒居住者
へと変化するのです。
その為、急性期病院や回復期病院では、患者様の疾患、身体機能へアプローチすることが多い一方、
退院すると生活をしないといけないため、生活に対してアプローチしないといけません。
または生活できている方は趣味や仕事、社会活動など今まで行っていた生活を取り戻せるようアプローチしないといけません。
そのアプローチ方法に関しては、急性期・回復期病院と同じでよろしいのでしょうか?
答えはNoです。
いくらセラピストがテクニシャンだったとしても、それだけでは解決しないのが生活期リハです。
介入方法を間違ってしまうと、いつまでたっても問題点を解決できず、リハビリ人生を送ってしまう恐れがあります。
次回は、急性期・回復期リハビリと生活期リハビリについての違いを説明したいと思います。
コロナに負けるな!~飲食店編~
連日、コロナウイルスのニュースや自粛などでストレス溜まっていませんか?
私はこの機会をポジティブに捉えており、毎日読書したりライフプランを再検討したりしています。
特に読書はお勧めですよ!!
話は変わりますが、私は「食べ歩き」が趣味です。
カフェやもちろん、行きつけの居酒屋も食事が美味しい所しか行きません。
食に対するこだわりも強いです。
そんな中、居酒屋などの飲食店でテイクアウトを結構やっていますね。
Fastpickなどのアプリも開発され、テイクアウトしやすい環境が増えてきてます。
そんな中、テイクアウトしている飲食店で気になったことや要望があるので、簡単にまとめてみました。
分類としては、
①お酒がメインのお店(居酒屋、Barなど)
②肉系のお店(焼肉、ステーキ屋など)
③麺(ラーメン、沖縄そば)
になります。
①居酒屋やBar
・お酒とセットでおつまみを販売してほしい
・オリジナルのお酒(自家製梅酒的な)を販売してほしい
・テイクアウトだと、居酒屋マジックがばれる(基本味付け濃い目、もしくは美味しくない)
・刺身のテイクアウト(食中毒対策、提供方法が気になる)
・食中毒対策が出来ているか(刺身テイクアウト、卵系、弁当など保管方法)
②肉系のお店
・焼きたてが食べれないのが最大のデメリット
・出来立て弁当も販売が難しい
・食中毒対策をより気を付けないといけない
・生肉を販売できない(おうち焼肉セットなど)
③麺(ラーメン、沖縄そば)
沖縄そばに関しては、元々テイクアウトや通販をやっているお店が多いですよね。
なので、SNSやその他宣伝ツールを使用する事で、売り上げが伸ばせるのではと思いました(甘くはありませんが)
問題はラーメンです。
あまりテイクアウトのラーメン屋ってみた事ありません。
なので今回のコロナ騒動にて、ラーメン屋が淘汰される可能性もあります。
お店自体も3密のお店しかないので、営業も難しそう。
そんな感じでまとめてみました。
私が住んでる沖縄県沖縄市では、このようなサイトがあります。
イザ☆コザ
https://nakamako.info/takeout/
沖縄市の情報はもちろん、今回はテイクアウトやデリバリー可能なお店なども掲載されています。
私もフル活用です。
Fastpick
https://fast-pick.com/
私がこよなく愛する「上間天ぷら」「鳥玉」も加盟しています。
スマホで注文し、お店で手軽にテイクアウトできます。
これはコロナ終息後もぜひ活用したいサービスです。
自粛している中、楽しみなのは食事っていう方もいると思います。
テイクアウトの利点、欠点も理解しておかないといけないので、参考になればいいなと思っています。
私はこの機会をポジティブに捉えており、毎日読書したりライフプランを再検討したりしています。
特に読書はお勧めですよ!!
話は変わりますが、私は「食べ歩き」が趣味です。
カフェやもちろん、行きつけの居酒屋も食事が美味しい所しか行きません。
食に対するこだわりも強いです。
そんな中、居酒屋などの飲食店でテイクアウトを結構やっていますね。
Fastpickなどのアプリも開発され、テイクアウトしやすい環境が増えてきてます。
そんな中、テイクアウトしている飲食店で気になったことや要望があるので、簡単にまとめてみました。
分類としては、
①お酒がメインのお店(居酒屋、Barなど)
②肉系のお店(焼肉、ステーキ屋など)
③麺(ラーメン、沖縄そば)
になります。
①居酒屋やBar
・お酒とセットでおつまみを販売してほしい
・オリジナルのお酒(自家製梅酒的な)を販売してほしい
・テイクアウトだと、居酒屋マジックがばれる(基本味付け濃い目、もしくは美味しくない)
・刺身のテイクアウト(食中毒対策、提供方法が気になる)
・食中毒対策が出来ているか(刺身テイクアウト、卵系、弁当など保管方法)
②肉系のお店
・焼きたてが食べれないのが最大のデメリット
・出来立て弁当も販売が難しい
・食中毒対策をより気を付けないといけない
・生肉を販売できない(おうち焼肉セットなど)
③麺(ラーメン、沖縄そば)
沖縄そばに関しては、元々テイクアウトや通販をやっているお店が多いですよね。
なので、SNSやその他宣伝ツールを使用する事で、売り上げが伸ばせるのではと思いました(甘くはありませんが)
問題はラーメンです。
あまりテイクアウトのラーメン屋ってみた事ありません。
なので今回のコロナ騒動にて、ラーメン屋が淘汰される可能性もあります。
お店自体も3密のお店しかないので、営業も難しそう。
そんな感じでまとめてみました。
私が住んでる沖縄県沖縄市では、このようなサイトがあります。
イザ☆コザ
https://nakamako.info/takeout/
沖縄市の情報はもちろん、今回はテイクアウトやデリバリー可能なお店なども掲載されています。
私もフル活用です。
Fastpick
https://fast-pick.com/
私がこよなく愛する「上間天ぷら」「鳥玉」も加盟しています。
スマホで注文し、お店で手軽にテイクアウトできます。
これはコロナ終息後もぜひ活用したいサービスです。
自粛している中、楽しみなのは食事っていう方もいると思います。
テイクアウトの利点、欠点も理解しておかないといけないので、参考になればいいなと思っています。
短時間通所リハの紹介 ~立ち上げ編~
おはようございます!
今日も介護保険分野の事について書かせていただきます!
前回のブログ
⇒https://terusyu.ti-da.net/e11468543.html
今日は、どのようにして立ち上げたかをご紹介したいと思います。
結論をから言いますと、
「私と上司以外、みんな立ち上げ反対」
でした。
なぜそのような結論になったかと言いますと、ミーティングやアンケート結果にて
①今の現状に満足している
②今の現状がいっぱいいっぱい
というセラピストからの回答が多数を示していました。
しかし現実は・・・・・
①平成28年度診療報酬改定による収益ダウン(要介護被保険者の維持期リハ 40%減収)
②外来リハ患者の修了者減少
③②に伴い新患数の減少(受け入れ枠の減少)
④前年度と比べ人件費高騰
という外来リハにとって耳が痛い現状がのしかかっていました。
これらの事をふまえ再度外来リハスタッフへ現状を伝達し、さらには通所リハにおける問題点を提起したうえで、
「40代、50代の要介護被保険者でも生きやすいデイケア作り」を認めてもらいました。
そして今度は、外来リハ患者様へのアンケートも実施。
そこで見えてきたのは、
・通所リハは高齢者が多くて行きたくない
・今の環境を変えたくない
・ほかの所だとリハの質が落ちる
ということが分かりました。
これは厚労省がアンケートを行った結果とも被る部分があると思います。
そこで当初は法人内デイケアに短時間通所リハを立ち上げる予定でしたが、
外来リハ患者様の心理的抵抗感を減らす目的と、
制度を大いに生かし、
外来リハに併設する形で短時間通所リハを立ち上げることになりました。
場所の確保は出来ましたが、次に待っていた問題は「短時間通所リハのコンセプト立案と周知」です。
これが結構苦労しました。
新しいことをやる場合、これが出来ていないと全く物事が進まないし、協力も得られにくいです。
なので次回はコンセプト立案についてブログを書きたいと思います。
今日も介護保険分野の事について書かせていただきます!
前回のブログ
⇒https://terusyu.ti-da.net/e11468543.html
今日は、どのようにして立ち上げたかをご紹介したいと思います。
結論をから言いますと、
「私と上司以外、みんな立ち上げ反対」
でした。
なぜそのような結論になったかと言いますと、ミーティングやアンケート結果にて
①今の現状に満足している
②今の現状がいっぱいいっぱい
というセラピストからの回答が多数を示していました。
しかし現実は・・・・・
①平成28年度診療報酬改定による収益ダウン(要介護被保険者の維持期リハ 40%減収)
②外来リハ患者の修了者減少
③②に伴い新患数の減少(受け入れ枠の減少)
④前年度と比べ人件費高騰
という外来リハにとって耳が痛い現状がのしかかっていました。
これらの事をふまえ再度外来リハスタッフへ現状を伝達し、さらには通所リハにおける問題点を提起したうえで、
「40代、50代の要介護被保険者でも生きやすいデイケア作り」を認めてもらいました。
そして今度は、外来リハ患者様へのアンケートも実施。
そこで見えてきたのは、
・通所リハは高齢者が多くて行きたくない
・今の環境を変えたくない
・ほかの所だとリハの質が落ちる
ということが分かりました。
これは厚労省がアンケートを行った結果とも被る部分があると思います。
そこで当初は法人内デイケアに短時間通所リハを立ち上げる予定でしたが、
外来リハ患者様の心理的抵抗感を減らす目的と、
制度を大いに生かし、
外来リハに併設する形で短時間通所リハを立ち上げることになりました。
場所の確保は出来ましたが、次に待っていた問題は「短時間通所リハのコンセプト立案と周知」です。
これが結構苦労しました。
新しいことをやる場合、これが出来ていないと全く物事が進まないし、協力も得られにくいです。
なので次回はコンセプト立案についてブログを書きたいと思います。
短時間通所リハの紹介 ~きっかけ編~
皆さん、お久しぶりです。
そしてはじめまして!
私は沖縄県で短時間通所リハを立ち上げた理学療法士です。
今日は私たち短時間通所リハの紹介をしたいと思います。
立ち上げたきっかけ 「ある1人の外来患者との出会い」
当時、外来リハで明らかに自宅環境に問題がありそうな女性の方を担当しました。
介護保険サービスへの移行を進めるも、年齢が若く(40代前半)、
「デイケアとかデイサービスはおじいおばあが行くところ。私たちみたいな年齢の人は介護保険を持っていても行く場所がないから、外来リハへ通っているんだよ」と言われました。
そしてある日、法人内のデイケアへフォロー行くとき、初めて現実を見ました。
・75歳以上と思われる方々が圧倒的に多い。
・そもそも40代、50代いない
・レクしてる
・ぼーっと座ってる人もいる
40代といえば、人生の半ばでまだまだやりたいことも沢山あるはず。
そんな中で脳卒中になり片麻痺という後遺症を持ってしまった。
でも、後遺症を持っててもやりたいこと沢山あるのに、あのような環境に行くと、良くなるものも良くならなさそうな気持ちは分かる気がします。
要介護被保険者の維持期リハ患者と言えば、平成24年頃から「介護保険への移行」がささやかれていました。
この方がもし外来リハを使えずに介護保険へ移行したらどうなるんだろうと考えた時、ふと思いました。
「若い人が来やすい通所リハを作ればいいじゃん!」と。
そしてその思いの一歩二歩先の思いを持っていた上司と出会いました。
次回、通所リハを作りたいと思った私がどのような流れで通所リハを作ったのか、書きたいと思います。
ありがとうございました!!
そしてはじめまして!
私は沖縄県で短時間通所リハを立ち上げた理学療法士です。
今日は私たち短時間通所リハの紹介をしたいと思います。
立ち上げたきっかけ 「ある1人の外来患者との出会い」
当時、外来リハで明らかに自宅環境に問題がありそうな女性の方を担当しました。
介護保険サービスへの移行を進めるも、年齢が若く(40代前半)、
「デイケアとかデイサービスはおじいおばあが行くところ。私たちみたいな年齢の人は介護保険を持っていても行く場所がないから、外来リハへ通っているんだよ」と言われました。
そしてある日、法人内のデイケアへフォロー行くとき、初めて現実を見ました。
・75歳以上と思われる方々が圧倒的に多い。
・そもそも40代、50代いない
・レクしてる
・ぼーっと座ってる人もいる
40代といえば、人生の半ばでまだまだやりたいことも沢山あるはず。
そんな中で脳卒中になり片麻痺という後遺症を持ってしまった。
でも、後遺症を持っててもやりたいこと沢山あるのに、あのような環境に行くと、良くなるものも良くならなさそうな気持ちは分かる気がします。
要介護被保険者の維持期リハ患者と言えば、平成24年頃から「介護保険への移行」がささやかれていました。
この方がもし外来リハを使えずに介護保険へ移行したらどうなるんだろうと考えた時、ふと思いました。
「若い人が来やすい通所リハを作ればいいじゃん!」と。
そしてその思いの一歩二歩先の思いを持っていた上司と出会いました。
次回、通所リハを作りたいと思った私がどのような流れで通所リハを作ったのか、書きたいと思います。
ありがとうございました!!
間違ったダイエット方法
最近、ダイエットがマイブームの照屋です。
ただマイブームの割には結果が伴っていませんが(笑)
自分が運営している通所リハでも月1で体組成検査を行っているんですが、
基準の体重、基礎代謝、体脂肪、内臓脂肪、筋肉量をクリアしている人は一人もいません!!
というかすべてクリアしてたら健康でそもそも医療保険や介護保険の世話にはなってないかもしれませんね。
今回、体重増加が原因で両下肢の痺れが強くなっちゃった方のダイエットをサポートさせていただきました。
この方は、入院中は順調にダイエット出来ていたものの、退院後から体重が減らなくなり、しまいにはリバウンドをしちゃったという流れです。
退院後1年で8キロ太っちゃいました。
かかりつけ医の先生をはじめ、色々な方に「痩せないとまた痛み強くなっちゃうよ」と脅され、入院時のように食事量を減らしダイエットを始めたとのこと。
しかし、ダイエットして3ヶ月経っても1キロ痩せるどころか、1キロ増えるハメに。
本人は、「食事控えているのに何で太るの?」と少々戸惑い気味な感じになっちゃいました。
太った原因って何だと思いますか??
問診をしたところ、この方はダイエットで1番やってはいけない間違いをおかしていたのをはじめ、3点ほど太る原因が見つかりました。
1つ目
この方は、「食事制限」をしていたのが間違っていたのです。
ダイエットには食事制限ってつきものでしょ?って思った方いませんか??
カロリー制限による食事療法は、痩せはしますがリバウンドしやすい方法にもなっています。
細かい話は省略し、カロリー制限ダイエットは、太りやすくなるホルモンがドバドバっと出やすくなっちゃうので、リバウンドは勿論、
次のダイエットでは痩せにくくなる原因にもなっちゃいます。
もし食事療法を行うのであれば、適度な糖質制限がいいと思われます。
ただ、糖質制限は専門の方の指導を受けてから行った方がいいと思います。
ってことで、カロリー制限ダイエット辞めさせました。
夕飯の炭水化物を減らし、おかず量が極端に少なかったので、おかずを2-3人前作るよう指導しました。
余ったおかずは、自分への弁当として時々持ってきてくれました。→お昼代の節約になりました(笑)
糖質を減らし、カロリーは維持した状態でダイエットを行いました。
2つ目
この方は、「痺れ」が原因で歩行障害が起こり、介護保険が必要になった方です。
処方薬を聞いてみると、リリカを飲んでいました。
でもリリカは効いていないけど、飲み続けているとのこと(半年ほど)。
リリカって調べてみたら副作用で太るみたいっすね。
まぁ副作用なんで全員に当てはまるわけではないんですが、そもそも副作用も気になるけど効いてもいない薬を半年も飲み続けるってどうなのかなって思いました。
もしかしたらリリカが原因で太りやすくなっている可能性があったので、次の診察でかかりつけ医に相談するよう伝えました。
ちなみに、痛みに関しては靴や装具にインソールを施すことで痺れの軽減が見られ、現在も改善傾向です。
3つ目
ストレス。
まぁ痺れもあったり太ったりもしたらストレスは増えそうですよね。
しかしこの方は身近に最大のストレス元がありました。
この方のご家族は動物愛護団体みたいなのに所属しており、野良猫を拾って里親を探す事業を行っているとのこと。
ただ野良猫を預かっているのはこのご家族ではなく、利用者本人。
利用者は犬を飼っており、野良猫が家に来ると、愛犬がギャンギャン吠えたり、また餌代もかかるし、別の野良猫が自宅周りにうろついたりして、ご近所迷惑にもなっているとのこと。
なので、ご家族と面談し、野良猫の世話が凄くストレスになっている事を伝え、家族会議を開いてもらいました。
以上の3点を改善しました。
結果、
①3ヶ月で-5キロ(ピーク時と比べて)
②痺れの改善
③睡眠の質UP
④猫もいなくなったので、愛犬との散歩が楽しくて仕方がない。
と改善が得られました。
ちなみに、自分は担当でも何でもなく、ダイエットの支援をさせていただいただけです。
ダイエットだけでこのような成果が得られたので、凄くやってて楽しかったです。
もちろんダイエットは人それぞれ原因は違います。
テレビの情報を鵜呑みにするだけでは痩せません。
自分に合ったダイエットを選ぶ事も大事ですが、ダイエットに関する正しい知識を持つ必要があると思います。
こんなブログを書きながら当の本人は全然結果が出ないので、悩んでます。。。。。
(ダイエット始めて2カ月目。-0.4キロ)
でも旧盆も太らずに乗り切ったから、これからまたダイエットがんばろ~
ただマイブームの割には結果が伴っていませんが(笑)
自分が運営している通所リハでも月1で体組成検査を行っているんですが、
基準の体重、基礎代謝、体脂肪、内臓脂肪、筋肉量をクリアしている人は一人もいません!!
というかすべてクリアしてたら健康でそもそも医療保険や介護保険の世話にはなってないかもしれませんね。
今回、体重増加が原因で両下肢の痺れが強くなっちゃった方のダイエットをサポートさせていただきました。
この方は、入院中は順調にダイエット出来ていたものの、退院後から体重が減らなくなり、しまいにはリバウンドをしちゃったという流れです。
退院後1年で8キロ太っちゃいました。
かかりつけ医の先生をはじめ、色々な方に「痩せないとまた痛み強くなっちゃうよ」と脅され、入院時のように食事量を減らしダイエットを始めたとのこと。
しかし、ダイエットして3ヶ月経っても1キロ痩せるどころか、1キロ増えるハメに。
本人は、「食事控えているのに何で太るの?」と少々戸惑い気味な感じになっちゃいました。
太った原因って何だと思いますか??
問診をしたところ、この方はダイエットで1番やってはいけない間違いをおかしていたのをはじめ、3点ほど太る原因が見つかりました。
1つ目
この方は、「食事制限」をしていたのが間違っていたのです。
ダイエットには食事制限ってつきものでしょ?って思った方いませんか??
カロリー制限による食事療法は、痩せはしますがリバウンドしやすい方法にもなっています。
細かい話は省略し、カロリー制限ダイエットは、太りやすくなるホルモンがドバドバっと出やすくなっちゃうので、リバウンドは勿論、
次のダイエットでは痩せにくくなる原因にもなっちゃいます。
もし食事療法を行うのであれば、適度な糖質制限がいいと思われます。
ただ、糖質制限は専門の方の指導を受けてから行った方がいいと思います。
ってことで、カロリー制限ダイエット辞めさせました。
夕飯の炭水化物を減らし、おかず量が極端に少なかったので、おかずを2-3人前作るよう指導しました。
余ったおかずは、自分への弁当として時々持ってきてくれました。→お昼代の節約になりました(笑)
糖質を減らし、カロリーは維持した状態でダイエットを行いました。
2つ目
この方は、「痺れ」が原因で歩行障害が起こり、介護保険が必要になった方です。
処方薬を聞いてみると、リリカを飲んでいました。
でもリリカは効いていないけど、飲み続けているとのこと(半年ほど)。
リリカって調べてみたら副作用で太るみたいっすね。
まぁ副作用なんで全員に当てはまるわけではないんですが、そもそも副作用も気になるけど効いてもいない薬を半年も飲み続けるってどうなのかなって思いました。
もしかしたらリリカが原因で太りやすくなっている可能性があったので、次の診察でかかりつけ医に相談するよう伝えました。
ちなみに、痛みに関しては靴や装具にインソールを施すことで痺れの軽減が見られ、現在も改善傾向です。
3つ目
ストレス。
まぁ痺れもあったり太ったりもしたらストレスは増えそうですよね。
しかしこの方は身近に最大のストレス元がありました。
この方のご家族は動物愛護団体みたいなのに所属しており、野良猫を拾って里親を探す事業を行っているとのこと。
ただ野良猫を預かっているのはこのご家族ではなく、利用者本人。
利用者は犬を飼っており、野良猫が家に来ると、愛犬がギャンギャン吠えたり、また餌代もかかるし、別の野良猫が自宅周りにうろついたりして、ご近所迷惑にもなっているとのこと。
なので、ご家族と面談し、野良猫の世話が凄くストレスになっている事を伝え、家族会議を開いてもらいました。
以上の3点を改善しました。
結果、
①3ヶ月で-5キロ(ピーク時と比べて)
②痺れの改善
③睡眠の質UP
④猫もいなくなったので、愛犬との散歩が楽しくて仕方がない。
と改善が得られました。
ちなみに、自分は担当でも何でもなく、ダイエットの支援をさせていただいただけです。
ダイエットだけでこのような成果が得られたので、凄くやってて楽しかったです。
もちろんダイエットは人それぞれ原因は違います。
テレビの情報を鵜呑みにするだけでは痩せません。
自分に合ったダイエットを選ぶ事も大事ですが、ダイエットに関する正しい知識を持つ必要があると思います。
こんなブログを書きながら当の本人は全然結果が出ないので、悩んでます。。。。。
(ダイエット始めて2カ月目。-0.4キロ)
でも旧盆も太らずに乗り切ったから、これからまたダイエットがんばろ~
デイケア学会in熊本
おはようございます
台風の影響もありましたが、無事に沖縄へ戻って来れました。
結果的にいつもの時間でも飛行機飛んでて大丈夫だったじゃん!って感じにはなりましたが、結果的に安全に早く沖縄に戻れたので、時間を有意義に使えて良かったです。
水曜日は熊本城のふもとにある観光地で研修会。


通所リハ計画書を多職種で考える内容。
視点が様々で勉強になったけど、視点が様々過ぎてまとまらなかったのが反省ですな。
でも、色々と他の事業所に悩みを聞いてもらえたし、自分らのやってる方向性は間違ってないなってのも分かったので良かったです。
木曜・金曜は学会でした。

木曜はポスター発表。

抄録の所属名を間違えるハプニングもありましたが、無事に発表終えて、活発な情報交換も出来ました。
学会では、活動と参加に着目した上で様々なアプローチ方法を紹介していました。
自分たち短リハもやってる事、方向性は間違ってなかったけど、もう一歩先を見据えたアプローチしないといけないなと反省もありました。
また家屋調査のセミナーでは、今まで見落としてたポイントも学べて、凄く充実しました。
これをどのようにして院内に取り入れて行くか吟味し、より良いサービス提供が出来るようにしたいと思います。
熊本ではあまり食を楽しめなかった中、美味しい食べ物とも出会えました。
ホテルの朝食のダゴ汁

馬刺しは毎日食べてました。でも値段が高すぎ!


又吉先生に紹介してもらった「宮ふく」のサトイモ。めちゃくちゃ美味くて、熊本で1番美味しかったかも。

博多に戻って「shin-shin」のラーメン。久々だったけど美味かった!

まぁ、何とも中身の薄いブログになりましたが、まとめると「無事に沖縄戻ってこれたのが良かった」です。月曜日からの仕事頑張れそう。
それではまた!
台風の影響もありましたが、無事に沖縄へ戻って来れました。
結果的にいつもの時間でも飛行機飛んでて大丈夫だったじゃん!って感じにはなりましたが、結果的に安全に早く沖縄に戻れたので、時間を有意義に使えて良かったです。
水曜日は熊本城のふもとにある観光地で研修会。


通所リハ計画書を多職種で考える内容。
視点が様々で勉強になったけど、視点が様々過ぎてまとまらなかったのが反省ですな。
でも、色々と他の事業所に悩みを聞いてもらえたし、自分らのやってる方向性は間違ってないなってのも分かったので良かったです。
木曜・金曜は学会でした。

木曜はポスター発表。

抄録の所属名を間違えるハプニングもありましたが、無事に発表終えて、活発な情報交換も出来ました。
学会では、活動と参加に着目した上で様々なアプローチ方法を紹介していました。
自分たち短リハもやってる事、方向性は間違ってなかったけど、もう一歩先を見据えたアプローチしないといけないなと反省もありました。
また家屋調査のセミナーでは、今まで見落としてたポイントも学べて、凄く充実しました。
これをどのようにして院内に取り入れて行くか吟味し、より良いサービス提供が出来るようにしたいと思います。
熊本ではあまり食を楽しめなかった中、美味しい食べ物とも出会えました。
ホテルの朝食のダゴ汁

馬刺しは毎日食べてました。でも値段が高すぎ!


又吉先生に紹介してもらった「宮ふく」のサトイモ。めちゃくちゃ美味くて、熊本で1番美味しかったかも。

博多に戻って「shin-shin」のラーメン。久々だったけど美味かった!

まぁ、何とも中身の薄いブログになりましたが、まとめると「無事に沖縄戻ってこれたのが良かった」です。月曜日からの仕事頑張れそう。
それではまた!
タグ :デイケア学会
グラインダー到着、インソールトラブル
おはようございます。
日曜の朝いかがお過ごしですか??
自分は日曜日の午前中が大好きで、ゆっくりする事も出来るし、作業するにも集中できるし、何かしら充実できるのでこの時間が好きです。
さて、さっそく本題ですが、今週ついに楽しみにしていたものが届きました!

グラインダー!!
インソール作成には欠かせないアイテム。
先日、入谷式インソールの講習会に参加し、グラインダーの必要性を実感。
DYMOCOインソールはグラインダーなしでも出来るが、履き心地を求めるのであればグラインダーは必須だし、微調整にも必要だし。
しかし、インソール用のグラインダーは高価で、院内でまだインソールの実績を残していないので購入伺いも厳しそうだし、正直どうしようかなと感がていました。
そしたら先日の入谷式インソールの講習会で、手作りグラインダーを作っている方を紹介していただき、速攻で連絡。
そして今週ついに完成し、受け取りました。
これで物はそろったのであとは削る練習して実践するだけですね。
※8月いっぱいまでは仕事以外の用事が立て込んでいるため、新規のインソール作成全てをお断りさせていただいています。
最近、インソール関係のトラブル相談が増えてます。
例えば、オーダーメイドインソールを履くことで歩行時の動揺が増え、痛みが出てしまう方。
オーダーメイドインソールを履くことでバランスを崩し転倒しそうになる方など。
そもそもオーダーメイドインソール履いて症状が悪化するって、どんな作り方したんだろうって思います。
個人的な見解ですが、
インソールって大きく作り方が以下の2つに分かれていると思います。
①型取りして作成する。
②姿勢、歩行を分析して、動きに合わせた型を作成する。
①の作り方は型取りしてるのでフィット感抜群だと思います。それにより指にも力が入りやすくなります。しかし何か不具合が生じると修正が難しい印象あり。あと、〇〇の症状には●●といった法則がある印象もあります。
②動きに合わせて作るので、動きやすくなります。しかし、動作分析力やインソール作成のセンスが問われるので、思うようにインソールを作成できない方も少なくはない。ただ簡単に作成できるため、修正も簡単に行いやすいので、状況に合わせたインソールが作れる。
①のインソールって大型ショップ、大手メーカー、義肢装具士がよく作る方法だと思います。
別のその方が悪いと言っているわけではないんですが、①の方法だろうが②の方法だろうが、作った後のアフターケアって大事だなって思います。作って終わりではなく、インソールを作って2週間~1ヶ月ぐらい履くことで、インソールが体に馴染んでくるので、その時に問題の症状がどうなってるかっていう判断を行わないといけないと思っています。
②のインソールは主にセラピストが作成するインソールだと思います。評価を行ったうえで作成するので、そもそも必要のない人にはインソールは作成しません。例えば膝痛がある人にも必要がなければインソールは作りません。更にセラピストが作るインソールが多いため、治療の過程で作るケースが多いので、アフターケアも十分に行えます。
ただし、フィット感が損なわれたり、作る人の技術力が問われるので、せっかくインソール作っても思うような効果が出なかったり、マメやタコなどの別の問題が生じたりする可能性も少なくありません。
ちなみに今回、インソールトラブルがあったのは①の作成方法で処方されたインソールでした。
値段も結構な値段でした。。。。。。(自分が案内している値段の7-8倍の値段)
がっちり素材で作られていたので、自分の技術、知識では修正不可能。
皆さんもインソールを作成する際は、作成方法をしっかり観察し、アフターケアもしっかり行いましょう!!
日曜の朝いかがお過ごしですか??
自分は日曜日の午前中が大好きで、ゆっくりする事も出来るし、作業するにも集中できるし、何かしら充実できるのでこの時間が好きです。
さて、さっそく本題ですが、今週ついに楽しみにしていたものが届きました!
グラインダー!!
インソール作成には欠かせないアイテム。
先日、入谷式インソールの講習会に参加し、グラインダーの必要性を実感。
DYMOCOインソールはグラインダーなしでも出来るが、履き心地を求めるのであればグラインダーは必須だし、微調整にも必要だし。
しかし、インソール用のグラインダーは高価で、院内でまだインソールの実績を残していないので購入伺いも厳しそうだし、正直どうしようかなと感がていました。
そしたら先日の入谷式インソールの講習会で、手作りグラインダーを作っている方を紹介していただき、速攻で連絡。
そして今週ついに完成し、受け取りました。
これで物はそろったのであとは削る練習して実践するだけですね。
※8月いっぱいまでは仕事以外の用事が立て込んでいるため、新規のインソール作成全てをお断りさせていただいています。
最近、インソール関係のトラブル相談が増えてます。
例えば、オーダーメイドインソールを履くことで歩行時の動揺が増え、痛みが出てしまう方。
オーダーメイドインソールを履くことでバランスを崩し転倒しそうになる方など。
そもそもオーダーメイドインソール履いて症状が悪化するって、どんな作り方したんだろうって思います。
個人的な見解ですが、
インソールって大きく作り方が以下の2つに分かれていると思います。
①型取りして作成する。
②姿勢、歩行を分析して、動きに合わせた型を作成する。
①の作り方は型取りしてるのでフィット感抜群だと思います。それにより指にも力が入りやすくなります。しかし何か不具合が生じると修正が難しい印象あり。あと、〇〇の症状には●●といった法則がある印象もあります。
②動きに合わせて作るので、動きやすくなります。しかし、動作分析力やインソール作成のセンスが問われるので、思うようにインソールを作成できない方も少なくはない。ただ簡単に作成できるため、修正も簡単に行いやすいので、状況に合わせたインソールが作れる。
①のインソールって大型ショップ、大手メーカー、義肢装具士がよく作る方法だと思います。
別のその方が悪いと言っているわけではないんですが、①の方法だろうが②の方法だろうが、作った後のアフターケアって大事だなって思います。作って終わりではなく、インソールを作って2週間~1ヶ月ぐらい履くことで、インソールが体に馴染んでくるので、その時に問題の症状がどうなってるかっていう判断を行わないといけないと思っています。
②のインソールは主にセラピストが作成するインソールだと思います。評価を行ったうえで作成するので、そもそも必要のない人にはインソールは作成しません。例えば膝痛がある人にも必要がなければインソールは作りません。更にセラピストが作るインソールが多いため、治療の過程で作るケースが多いので、アフターケアも十分に行えます。
ただし、フィット感が損なわれたり、作る人の技術力が問われるので、せっかくインソール作っても思うような効果が出なかったり、マメやタコなどの別の問題が生じたりする可能性も少なくありません。
ちなみに今回、インソールトラブルがあったのは①の作成方法で処方されたインソールでした。
値段も結構な値段でした。。。。。。(自分が案内している値段の7-8倍の値段)
がっちり素材で作られていたので、自分の技術、知識では修正不可能。
皆さんもインソールを作成する際は、作成方法をしっかり観察し、アフターケアもしっかり行いましょう!!
遅めの母の日
みなさんこんばんは!
最近、Bリーグにめちゃんこハマりまくってる照屋です。
キングスは惜しくもクォーターファイナルでシーホース三河に負けちゃいましたが、来シーズンこそはやってくれるでしょう!!
Bリーグにハマってからは週末=バスケ観戦ばっかしてたので、勉強会にも行ってませんでした(笑)
でも勉強会に行くだけが勉強ではないんで、平日はしっかり色んな本読んだり、ブログ読んだり、YouTube見たりして勉強してました♪
Bリーグも終わったんで、6月にあるインソール関連のセミナー2つを控えているんですが、再びインソールの勉強を始めました。
去年の今頃は「院内でインソールチームを立ち上げる!」と豪語しておきながら、
短時間通所リハの立ち上げや披露宴の準備で、それどころではありませんでした(笑)
今年もインソールチームを後輩PTのT君と二人で細々と立ち上げる事にしました。
そんなこんなで、最近インソールを作る機会が増えてきてるんですが、母親から相談が。。。。
「最近、ウォーキングしてたら右膝が痛くなる」
「プールの先生に勧められた筋トレしてるけど、良くならないしむしろ悪くなっている」
と相談されました。
そして先日、シーミーがあった時にふと母親の歩き方を見てたら・・・・・
「ん??靴おかしくない??」と異変に気付きました。
ってことで、母の日のプレゼントは新しい靴+インソールをプレゼントしました。
「履きなれた靴が歩きやすくて」と、母親はここ数カ月、膝が痛いのを我慢しながらこの靴履いて、ウォーキングしていたそうです。


歩き方を評価し、インソールを作成。
同じ生活環境だったのか、母親と自分の歩き方が似ているのを発見。
なので、インソール作成もイメージしやすかったです(笑)
最近、健康志向が高まりつつある沖縄ですが、ウォーキングとかランニングで痛みが出てしまう方は、一度靴をチェックすることをお勧めしますよ♪
それでは明日からまた1週間始まるので、ちばっていきましょー!!
最近、Bリーグにめちゃんこハマりまくってる照屋です。
キングスは惜しくもクォーターファイナルでシーホース三河に負けちゃいましたが、来シーズンこそはやってくれるでしょう!!
Bリーグにハマってからは週末=バスケ観戦ばっかしてたので、勉強会にも行ってませんでした(笑)
でも勉強会に行くだけが勉強ではないんで、平日はしっかり色んな本読んだり、ブログ読んだり、YouTube見たりして勉強してました♪
Bリーグも終わったんで、6月にあるインソール関連のセミナー2つを控えているんですが、再びインソールの勉強を始めました。
去年の今頃は「院内でインソールチームを立ち上げる!」と豪語しておきながら、
短時間通所リハの立ち上げや披露宴の準備で、それどころではありませんでした(笑)
今年もインソールチームを後輩PTのT君と二人で細々と立ち上げる事にしました。
そんなこんなで、最近インソールを作る機会が増えてきてるんですが、母親から相談が。。。。
「最近、ウォーキングしてたら右膝が痛くなる」
「プールの先生に勧められた筋トレしてるけど、良くならないしむしろ悪くなっている」
と相談されました。
そして先日、シーミーがあった時にふと母親の歩き方を見てたら・・・・・
「ん??靴おかしくない??」と異変に気付きました。
ってことで、母の日のプレゼントは新しい靴+インソールをプレゼントしました。
「履きなれた靴が歩きやすくて」と、母親はここ数カ月、膝が痛いのを我慢しながらこの靴履いて、ウォーキングしていたそうです。
歩き方を評価し、インソールを作成。
同じ生活環境だったのか、母親と自分の歩き方が似ているのを発見。
なので、インソール作成もイメージしやすかったです(笑)
最近、健康志向が高まりつつある沖縄ですが、ウォーキングとかランニングで痛みが出てしまう方は、一度靴をチェックすることをお勧めしますよ♪
それでは明日からまた1週間始まるので、ちばっていきましょー!!
短時間通所リハビリテーションとは
お久しぶりです。
別に忙しかったわけでもないんですが、ネタがありすぎるくらい毎日が充実しています。
今年の1月から「短時間通所リハビリテーション」というのを立ち上げまして、その責任者として日々仕事をしています。
なので今日は簡単に短時間通所リハビリテーションについて立ち上げた経緯や通所リハの内容を書こうと思います。
通所リハとは?
短時間通所リハとは何?ってよく聞かれるんですけど、
短時間通所リハとは、簡単に言うと
「介護保険を使った通所リハサービスの1つ。」
「レクとか食事とか入浴とかいいんです。リハビリだけしたいんです」
っていう方にはもってこいの介護保険のリハビリサービスです。
「リハ特化型デイサービス」・「外来リハ」との違い
よく比較されるのが、「リハビリ特化型デイサービス」と「外来リハビリ」です。
まずリハビリ特化型デイサービスとの違いですが、リハビリ方針が違います。
そして何よりデイサービスなので、基本的にはリハビリはありません。あるのはリハビリではなく、機能訓練です。
なのでリハ特化型デイサービスは利用者の「体」を対象にリハビリをします(リハビリと言っていいのかは分かりませんが。。。。)
例えるならば介護保険を使ったフィットネスジム、整体、サロン、と言ったところでしょうか。
一方、短時間通所リハビリテーションなんですが、対象が利用者の「生活」「社会参加」なので、その目標に向かって機能訓練する人はするし、社会参加のきっかけ(旅リハ、外出プロジェクトなど)を与えたりします。生活環境も評価し、そのうえで必要な環境設定も行ったりします。
そして外来リハとの違いは、使っている保険の違いですかね。医療保険と介護保険。
医療保険は基本的には、「治す」ための保険です。
一方、介護保険は機能を維持・改善させながら、そのヒトらしく生活できるように自立支援を行う保険です。
外来リハでの問題
その外来リハで今一番に問題になっているのが、リハビリ算定日数期限を超えた方々のリハビリ提供方法です。
リハビリには算定日数期限というのが存在し、整形外科など運動器疾患は診断日より150日以内、脳卒中や脊髄損傷など脳血管疾患は発症日より180日以内と法律で定められています。
その期限を超えたらリハビリできないの?と聞かれますが、リハビリは可能です。
これには2つ方法があります。
まず、1つ目ですが、医師が「この人はまだ良くなるから、リハビリを続けた方がいい」と書類で算定日数期限を除外する方法です。
これを行うには医師と担当セラピストが毎月書類を書けばいいのですが、これには1つ条件があります。
それは「前月よりも必ず良くなっている証拠を証明しないといけない」という事です。
なので、筋力とか歩く速さとかはすぐに検査も出来るし比較するのが容易なため、よく歩行障害がある方は算定除外でリハビリしている方が多い中、高次脳機能障害がある方は検査ですら時間がかかってしまうため、訓練効果を示すのが難しいのが問題です。
次に2つ目ですが、「この人は良くなることはないけど、維持目的でのリハビリが必要だな」と主治医が判断すればリハビリ継続が出来ます。
この場合、書類は3ヶ月に1回書類を書けば大丈夫なんですが、先ほどの算定除外との違いは勿論あります。
それは、リハビリできる時間が決まっているということです。
算定除外は算定内リハと同様に1ヶ月に何回もやっていいんですが、この維持を目的としたリハビリは1ヶ月に260分と決まっています。
俗にいう「13単位以内」ってやつです。
1単位=20分、1回=2単位、で我々は提供していますが、予約の状況も踏まえ維持目的の方は1回/週のリハ頻度でリハビリを行います。
ここで問題なのが、医療保険は治すための保険にもかかわらず「維持期リハ」というのが提供されている事が問題なんです。
そこで国が目を付けたのが、「介護保険」を持っていて、なおかつ「維持期リハ」を行っている方です。
診療報酬改定
平成21年の介護報酬改定により、短時間通所リハビリテーションが新設されました。
これはどういうかというと、
「外来維持期リハビリをやっている人は、介護保険を使って短時間通所リハビリテーションへ移行させなさい」という内容でした。
そして平成22年の診療報酬改定より、維持期リハの方は介護保険のリハビリへと移行させなさいと明記されるようになりました。
しかーし!!
そんな簡単にうまくいくわけがありません。
なんせ、当時の通所リハビリというのは、ただマッサージして筋トレして歩いて物理療法して集団体操して・・・・・・
みたいな感じで、とても利用者の生活に着目したリハビリとは思えないような内容となっていました。
なので、利用者の心理的な抵抗が強く出て、中々行きたがらない人が少なくはなかったと言われています。
そして、平成26年度の診療報酬改定より、「介護保険を持っている維持期リハの方は、点数の1割を減算しますよ」「あなたの施設で介護保険の設備が整っていなかったら更に減算しますよ」という改定が行われました。
いわゆる減算措置ってやつです。
小さなクリニックなどは1割の減算でも経営に響くので、なるべく維持期リハを出さないようにと、算定期限が近くなると、半強制的にリハビリが終了となりました。大きな病院などはケースにもよるんですが、期限が切れても続ける人は続けました。それくらい経営的にはあまり響かない措置だったということでしょう。
そしてついに平成28年4月。国は更なる減算措置を実施しました。
それは、介護保険を持った維持期リハの方には、点数の4割減算。そして介護保険の設備が整っていなかったら更に減算。そしてそして、目標設定を主治医やセラピストと行わなかったら更にさらに減算という措置を取りました。
これをトリプル減算措置といい、最大点数の56%減算となります。
これは大きな病院でも収益に響き、維持期リハの方を終了させようと必死になっています。
維持期リハの問題点
この内容に関しては別日でまた書きたいと思います。
ただ一つ言えるのは、この状況を作ってしまったのはセラピストや医師だと思っています。
決してリハビリが下手くそとか声掛けがダメだったという訳ではありません。
むしろ患者さんからしたら感謝感謝雨嵐状態です。
この問題により、維持期リハが中々終わらないのかなと個人的には思っています。
悪い意味で信頼関係が深まった結果が、維持期リハが増え続けている原因だと思っています。
短リハ立ち上げた経緯
平成30年3月31日をもちまして、介護保険を持っている方は外来維持期リハが受けれなくなります。
なのでリハ継続したい方が介護保険のリハサービスへ移行しないといけなくなります。
そこで受け皿として私たちが短時間通所リハを立ち上げました。
私たちが取り組んでいる短時間通所リハですが、通所リハの負のイメージを払しょくできるよう、いくつかの取り組みを行っています。
①外来リハと同じスペースでリハサービスを提供。
そうなんです。短時間通所リハのみ、医療保険リハと場所が併用できるんです。なので、外来リハ使っていた方は慣れた環境でリハを出来るようになります。
②外来リハスタッフが短時間通所リハ利用者も見る
短時間通所リハのみ、医療と介護のリハビリを兼任することが出来ます。
そのため、今まで担当だった方や、担当ではないが見たことある方が短時間通所リハでも担当になってくれます。
③外来リハより良いサービスを提供します。
外来リハの強みは個別リハ介入時間が長いという事です(と言っても長くても40分ですが)。介護保険の個別介入時間は長くても30分~40分です。ただ個別リハビリだけがリハビリなのでしょうか??
違うと思います。
ここからが通所リハの強みです。通所リハは必ず自宅訪問を行います。
そのため、生活環境を把握することが出来ます。
はい、生活環境をチェックできることが通所リハ最大のメリットなんです。
そうすることで、その人の体もそうですが「生活」に着目したリハビリを提供することが可能となります。
なので、自宅環境を考慮した自主トレも提供できるし、具体的な目標設定も出来るので、リハビリを行う意味がより強くなります。
受け身のリハから、主導的なリハへの転換。
これが通所リハの強みだと思います。
そして、リハビリに特化した通所リハこそが「短時間通所リハ」だと思います。
④言語聴覚士の配置
結構、地域には高次脳機能障害や口腔内の問題がある方っているんですが、これってほとんど医療保険でしかリハビリ出来ないんですよね。というか通所リハや訪問リハに言語聴覚士が在籍している施設がとても少ないからです。
そこで言語聴覚士も配置し、言語聴覚士も地域に携われる環境を作っています。
コミュニケーションや食べる事が出来てこそ、色々な事にチャレンジできると思っています。
なので、言語聴覚士がいるというのはとても重要なことなんです。
この4点が私たちが立ち上げた短時間通所リハの取り組みです。
最後に
長くなりましたが、平成30年4月からは診療報酬と介護報酬の同時改定が行われます。
この改定が、2025年問題の指針にもなるくらい大事なことなんです。
この前、この大事な問題の会議中に森友学園の問題を切り出した民進党の議員にはとても失望しました。
それくらい大事な法案の審議なのに・・・・・・。
というぐらい、大きな変化が起こります。
なので柔軟に対応できるようにしていきたいと思います。
時代背景を読み取れないと、セラピストはどんどんおいて行かれるだけです。
色々と時代背景を読み解き、それに見合ったサービスを提供できるよう、努力していきましょう!!
別に忙しかったわけでもないんですが、ネタがありすぎるくらい毎日が充実しています。
今年の1月から「短時間通所リハビリテーション」というのを立ち上げまして、その責任者として日々仕事をしています。
なので今日は簡単に短時間通所リハビリテーションについて立ち上げた経緯や通所リハの内容を書こうと思います。
通所リハとは?
短時間通所リハとは何?ってよく聞かれるんですけど、
短時間通所リハとは、簡単に言うと
「介護保険を使った通所リハサービスの1つ。」
「レクとか食事とか入浴とかいいんです。リハビリだけしたいんです」
っていう方にはもってこいの介護保険のリハビリサービスです。
「リハ特化型デイサービス」・「外来リハ」との違い
よく比較されるのが、「リハビリ特化型デイサービス」と「外来リハビリ」です。
まずリハビリ特化型デイサービスとの違いですが、リハビリ方針が違います。
そして何よりデイサービスなので、基本的にはリハビリはありません。あるのはリハビリではなく、機能訓練です。
なのでリハ特化型デイサービスは利用者の「体」を対象にリハビリをします(リハビリと言っていいのかは分かりませんが。。。。)
例えるならば介護保険を使ったフィットネスジム、整体、サロン、と言ったところでしょうか。
一方、短時間通所リハビリテーションなんですが、対象が利用者の「生活」「社会参加」なので、その目標に向かって機能訓練する人はするし、社会参加のきっかけ(旅リハ、外出プロジェクトなど)を与えたりします。生活環境も評価し、そのうえで必要な環境設定も行ったりします。
そして外来リハとの違いは、使っている保険の違いですかね。医療保険と介護保険。
医療保険は基本的には、「治す」ための保険です。
一方、介護保険は機能を維持・改善させながら、そのヒトらしく生活できるように自立支援を行う保険です。
外来リハでの問題
その外来リハで今一番に問題になっているのが、リハビリ算定日数期限を超えた方々のリハビリ提供方法です。
リハビリには算定日数期限というのが存在し、整形外科など運動器疾患は診断日より150日以内、脳卒中や脊髄損傷など脳血管疾患は発症日より180日以内と法律で定められています。
その期限を超えたらリハビリできないの?と聞かれますが、リハビリは可能です。
これには2つ方法があります。
まず、1つ目ですが、医師が「この人はまだ良くなるから、リハビリを続けた方がいい」と書類で算定日数期限を除外する方法です。
これを行うには医師と担当セラピストが毎月書類を書けばいいのですが、これには1つ条件があります。
それは「前月よりも必ず良くなっている証拠を証明しないといけない」という事です。
なので、筋力とか歩く速さとかはすぐに検査も出来るし比較するのが容易なため、よく歩行障害がある方は算定除外でリハビリしている方が多い中、高次脳機能障害がある方は検査ですら時間がかかってしまうため、訓練効果を示すのが難しいのが問題です。
次に2つ目ですが、「この人は良くなることはないけど、維持目的でのリハビリが必要だな」と主治医が判断すればリハビリ継続が出来ます。
この場合、書類は3ヶ月に1回書類を書けば大丈夫なんですが、先ほどの算定除外との違いは勿論あります。
それは、リハビリできる時間が決まっているということです。
算定除外は算定内リハと同様に1ヶ月に何回もやっていいんですが、この維持を目的としたリハビリは1ヶ月に260分と決まっています。
俗にいう「13単位以内」ってやつです。
1単位=20分、1回=2単位、で我々は提供していますが、予約の状況も踏まえ維持目的の方は1回/週のリハ頻度でリハビリを行います。
ここで問題なのが、医療保険は治すための保険にもかかわらず「維持期リハ」というのが提供されている事が問題なんです。
そこで国が目を付けたのが、「介護保険」を持っていて、なおかつ「維持期リハ」を行っている方です。
診療報酬改定
平成21年の介護報酬改定により、短時間通所リハビリテーションが新設されました。
これはどういうかというと、
「外来維持期リハビリをやっている人は、介護保険を使って短時間通所リハビリテーションへ移行させなさい」という内容でした。
そして平成22年の診療報酬改定より、維持期リハの方は介護保険のリハビリへと移行させなさいと明記されるようになりました。
しかーし!!
そんな簡単にうまくいくわけがありません。
なんせ、当時の通所リハビリというのは、ただマッサージして筋トレして歩いて物理療法して集団体操して・・・・・・
みたいな感じで、とても利用者の生活に着目したリハビリとは思えないような内容となっていました。
なので、利用者の心理的な抵抗が強く出て、中々行きたがらない人が少なくはなかったと言われています。
そして、平成26年度の診療報酬改定より、「介護保険を持っている維持期リハの方は、点数の1割を減算しますよ」「あなたの施設で介護保険の設備が整っていなかったら更に減算しますよ」という改定が行われました。
いわゆる減算措置ってやつです。
小さなクリニックなどは1割の減算でも経営に響くので、なるべく維持期リハを出さないようにと、算定期限が近くなると、半強制的にリハビリが終了となりました。大きな病院などはケースにもよるんですが、期限が切れても続ける人は続けました。それくらい経営的にはあまり響かない措置だったということでしょう。
そしてついに平成28年4月。国は更なる減算措置を実施しました。
それは、介護保険を持った維持期リハの方には、点数の4割減算。そして介護保険の設備が整っていなかったら更に減算。そしてそして、目標設定を主治医やセラピストと行わなかったら更にさらに減算という措置を取りました。
これをトリプル減算措置といい、最大点数の56%減算となります。
これは大きな病院でも収益に響き、維持期リハの方を終了させようと必死になっています。
維持期リハの問題点
この内容に関しては別日でまた書きたいと思います。
ただ一つ言えるのは、この状況を作ってしまったのはセラピストや医師だと思っています。
決してリハビリが下手くそとか声掛けがダメだったという訳ではありません。
むしろ患者さんからしたら感謝感謝雨嵐状態です。
この問題により、維持期リハが中々終わらないのかなと個人的には思っています。
悪い意味で信頼関係が深まった結果が、維持期リハが増え続けている原因だと思っています。
短リハ立ち上げた経緯
平成30年3月31日をもちまして、介護保険を持っている方は外来維持期リハが受けれなくなります。
なのでリハ継続したい方が介護保険のリハサービスへ移行しないといけなくなります。
そこで受け皿として私たちが短時間通所リハを立ち上げました。
私たちが取り組んでいる短時間通所リハですが、通所リハの負のイメージを払しょくできるよう、いくつかの取り組みを行っています。
①外来リハと同じスペースでリハサービスを提供。
そうなんです。短時間通所リハのみ、医療保険リハと場所が併用できるんです。なので、外来リハ使っていた方は慣れた環境でリハを出来るようになります。
②外来リハスタッフが短時間通所リハ利用者も見る
短時間通所リハのみ、医療と介護のリハビリを兼任することが出来ます。
そのため、今まで担当だった方や、担当ではないが見たことある方が短時間通所リハでも担当になってくれます。
③外来リハより良いサービスを提供します。
外来リハの強みは個別リハ介入時間が長いという事です(と言っても長くても40分ですが)。介護保険の個別介入時間は長くても30分~40分です。ただ個別リハビリだけがリハビリなのでしょうか??
違うと思います。
ここからが通所リハの強みです。通所リハは必ず自宅訪問を行います。
そのため、生活環境を把握することが出来ます。
はい、生活環境をチェックできることが通所リハ最大のメリットなんです。
そうすることで、その人の体もそうですが「生活」に着目したリハビリを提供することが可能となります。
なので、自宅環境を考慮した自主トレも提供できるし、具体的な目標設定も出来るので、リハビリを行う意味がより強くなります。
受け身のリハから、主導的なリハへの転換。
これが通所リハの強みだと思います。
そして、リハビリに特化した通所リハこそが「短時間通所リハ」だと思います。
④言語聴覚士の配置
結構、地域には高次脳機能障害や口腔内の問題がある方っているんですが、これってほとんど医療保険でしかリハビリ出来ないんですよね。というか通所リハや訪問リハに言語聴覚士が在籍している施設がとても少ないからです。
そこで言語聴覚士も配置し、言語聴覚士も地域に携われる環境を作っています。
コミュニケーションや食べる事が出来てこそ、色々な事にチャレンジできると思っています。
なので、言語聴覚士がいるというのはとても重要なことなんです。
この4点が私たちが立ち上げた短時間通所リハの取り組みです。
最後に
長くなりましたが、平成30年4月からは診療報酬と介護報酬の同時改定が行われます。
この改定が、2025年問題の指針にもなるくらい大事なことなんです。
この前、この大事な問題の会議中に森友学園の問題を切り出した民進党の議員にはとても失望しました。
それくらい大事な法案の審議なのに・・・・・・。
というぐらい、大きな変化が起こります。
なので柔軟に対応できるようにしていきたいと思います。
時代背景を読み取れないと、セラピストはどんどんおいて行かれるだけです。
色々と時代背景を読み解き、それに見合ったサービスを提供できるよう、努力していきましょう!!
環境の変化

みなさん、こんにちは!!
久しぶりの投稿となります。
新年あけて、やがて1ヶ月が経とうとしていますが、皆さんは今年やりたい事を出来てますか??
そして楽しんでイキイキとした毎日過ごしていますか??
僕は、新年早々色々なイベントがあったため、少しだけ疲れていたのかヘルペスが出来たり風邪ひいたりと、踏んだり蹴ったりな毎日でした(笑)
なので披露宴のお礼に関しては、少し体調が整ってからさせていただきます。ご了承ください。
そんな感じですが、今日は「変化」について書かせてもらいます。
最近思うのは、変化するのって確かに怖い事だと思います。今までいた慣れた環境から離れる事になるんで。
でも、そうしないといけない状況になった時、そのままでいても状況が余計に悪くなるだけだと思います。
なので、変化って凄く勇気がいるんですが、必要なことだよ思います。
特に変化しないといけない状況にいる時こそ、変化って必要だなって思います。
変化した結果、状況が良くなるか悪くなるかは、正直やってみないと分かりません。
ただ、状況が悪くなったとしても、また変化すればいいだけなのかなって思います。
自分自身にとっては状況が悪くなっても、自分がまた変わらないといけないっていうチャンスだと思うので、
変化した結果、良くなろうが悪くなろうが、自分にとってはプラスになると思います。
人それぞれ価値観って違うと思うので、この考えが正解とは限りません。反対の意見も出てくるでしょう。
なので、皆さんに聞きたいです。
悪くもないが良くもない環境を0(ゼロ)とします。今あなたのいる環境がゼロの環境、もしくはマイナスの環境だとしたら、変化を恐れず環境を変えようと頑張ることが出来ますか?それとも環境が変わるまで(良くなるか悪くなるかは不明)、自分は何もせずじっと待ちますか?
それともゼロの環境が変わらないように頑張りますか??